いつの間にか英語学習できるゲームベスト10

秘密を知りたいですか?
実はゲームは、子供だけのものではないのです。
もう一つ秘密を知りたいですか?
ゲームは、英語を上達させるために大人の英語学習者が遊べる、効果的な学習道具なのです。
あらゆるゲームがあります!

秘密を知りたいですか?
実はゲームは、子供だけのものではないのです。
もう一つ秘密を知りたいですか?
ゲームは、英語を上達させるために大人の英語学習者が遊べる、効果的な学習道具なのです。
あらゆるゲームがあります!

英語の文法書にはすっかり疲れ果てましたか?
英語の練習問題は十分なほど繰り返してやりましたね?
これから家に帰って、またさらに英語学習をするなんてありえないと思っているのではないでしょうか。
ゆっくり座って、テレビをつけて、リラックスしたい。誰でもそんな風に思うでしょう。
そんなあなたに耳寄りの情報があります!
英語の単語力をつけたり、流暢な英語の話し方を学んだりできる最適な方法の一つは、英語のテレビ番組、シットコムを観ることなんです。
“Sitcom”(シットコム)とは …

説得力を持って効果的に英語で何かを伝えるためには、しっかりとした英文の構造を学ぶことが不可欠です。
自分の英文に自信が持てませんか?
短い脚が一本しかないイスのように、グラグラした文章になっていませんか?
文章がどのような部分からできており、どのように正しい順序で組み合わさっているかを理解していなければ、文章はバラバラになってしまうのです。
この記事では3つのステップに従って、文法的に正しい文章の書き方、話し方をお伝えします。

もし英語を話せたら、あなたは6つの全ての大陸で、誰かしらとコミュニケーションを取ることができるでしょう。
カナダの北の端からアフリカの南の先まで、英語を話している人々はいたるところにいるのです。
英語学習者にとって、これは耳寄りな情報ですね!
英語はまさにグローバルな言語です。これを学べば、友達や仕事上のコネクションの輪を世界中に広げることができるはずです。
こんなこと、あなたは既に知っているかもしれませんね。
では、もう少し具体的な話をしましょう。…
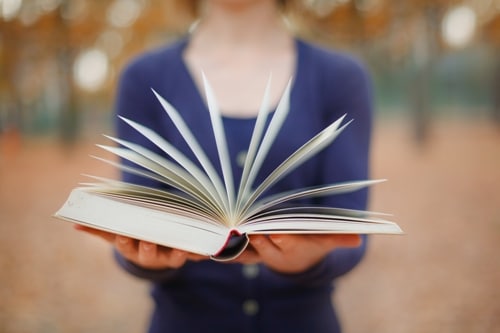
英語で本を読みたいと思ってもどこから手を付けて良いのか分からない、なんてことはありませか?
何百万もの本の中から1冊を選ぶのって大変ですよね。
では、どのような本から読み始めれば良いのでしょうか。
おすすめは、英語のネイティブスピーカーたちが読んでいる本です。
ベストセラーになる本は英語学習者にとっては難しすぎるように思えるかもしれません。しかし実は、人気の本はシンプルな英語で書かれていることが多いので、英語学習にも最適なのです。
本をベストセラーにするには、多くの人が読めるようにしなくてはいけません。つまり人気のある本は…

サンクスギビングのディナーは家族や友達と共にして、感謝と愛を伝えましょう!
1つ屋根の下で、美味しい食事をすることの素晴らしさを感じたのはいつですか?
時に私たちは、人生で出会う人々の存在や、自分に与えられている物事への感謝、そしてその幸せを忘れてしまいます。いつの間にかそれらが当たり前のもの…

ちょっとゲームをしましょう。
次の文章を声に出して読んでみてください。
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.…